みなさん、こんにちは。

入学・就職・転勤・転職など、新生活を迎えるとこれまでとは環境がガラリと変化しますね。

新生活を機に、犬をお迎えするご家庭も多いかと思います。


ただ、共働きであったり、一人暮らしであったりすると、思うように仕事が終わらず泣く泣く残業せざるを得ない日がやってくることも多々あります。

(本当は、残業しない生活が一番いいんですけどね!!)

ということで、我が家では毎週1回は「犬の幼稚園」に通園し、他の犬たちと関わりを持つ機会や基本コマンド・歯磨き・呼び戻し訓練などのトレーニングを1年半続けています。


この「犬の幼稚園」に関して、
【通う必要はあるの?】
【どんな風に使っているの?】
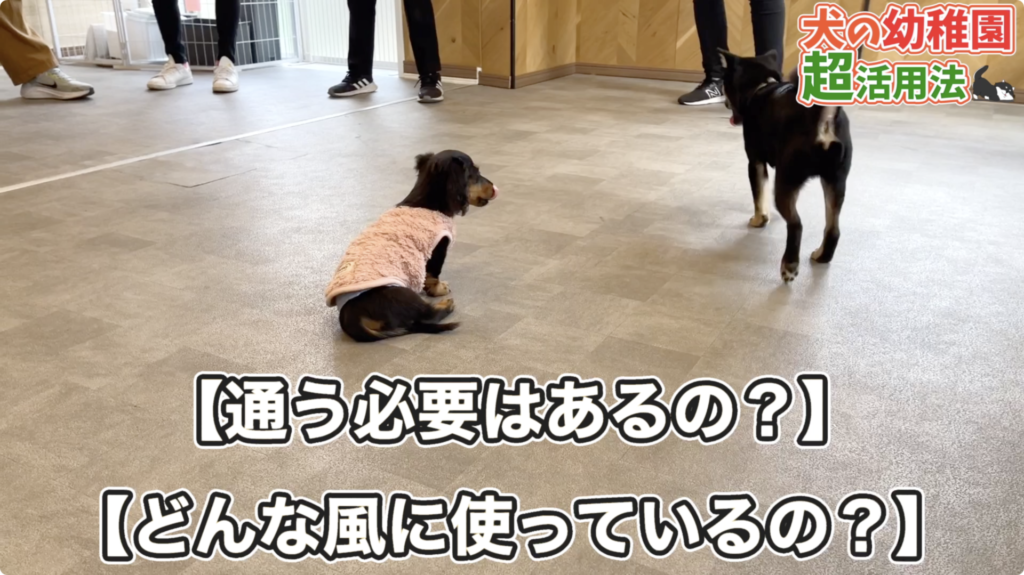
といった疑問を解消するため、実体験を基に、わかりやすくまとめてみました。

それでは、早速見ていきましょう!
動画で見る「犬の幼稚園超活用法」
本記事の内容は、YouTubeで公開しています!ぜひご覧くださいね!
入学・就職・転勤・転職など、新生活を迎えると環境がガラリと変化しますね。
中には、新生活を機に「犬をお迎えする」ご家庭も多いかと思います。
しかし、一人暮らしや共働きなどで仕事の帰りが遅くなり泣く泣く残業せざるを得ない日がやってくることも。
そうした場合に備えて、犬のしつけを行なってくれる「犬の幼稚園」を検討することになるかもしれません。
今回は、実際に柴犬を「犬の幼稚園」に通わせて1年半経過して、効果的だったトレーニングについて6つご紹介します。
また、「犬の幼稚園に通っても変化がない」とされる【本当の理由】について3つお伝えしたいと思います。
是非とも最後までご覧いただき、犬の幼稚園に通わせるかについてご参考になさってくださいね!
通園頻度

幼犬期には多くの刺激を受けてもらうため、最初の半年間ほどは週2回通園していました。
成犬を迎えた今では、通園頻度は週1日程度。

基本的なトレーニングだけでなく、プレイタイムやお昼寝もあり、健康的な1日を過ごすことができることに安心して通わせています。

「褒めるしつけ」を主体とした幼稚園であるため、本人も幼稚園に通うことはまんざらでもないようです。
また、ほぼ固定の曜日に通園しているため、特に仲良しのお友達もできている様子が伺えます。

実際に1年半通う中で、特に効果を実感したトレーニングを6つご紹介します。


主なトレーニング内容
歯磨き習慣

初めて犬を飼う場合は、どうしても直面するこの問題。
そう、「歯磨き」

犬の扱いに慣れている飼い主さんはちゃちゃっと指磨きや歯ブラシでの口腔ケアを毎日行えますが、初めて犬を飼う方は不慣れ故に口を触ることさえ難しいことも。

そのため、幼犬期から歯磨き習慣をつけるため、幼稚園に通園するたび必ず歯磨きの練習をしてもらっていました。


仰向けになって歯磨きをするパターンや、首輪をつけて歯磨きをするパターンなど、状況に応じた練習をしてくれていました。

その甲斐あってか、今では毎日歯磨きをして、獣医師の先生に褒められるほどピカピカの歯をキープしています。


呼び戻し

ドッグランでは犬が遠くへ行ってしまうことも多々あります。
そうした時に、「呼び戻し」ができると、遠くにいても犬を呼び寄せることが可能です。
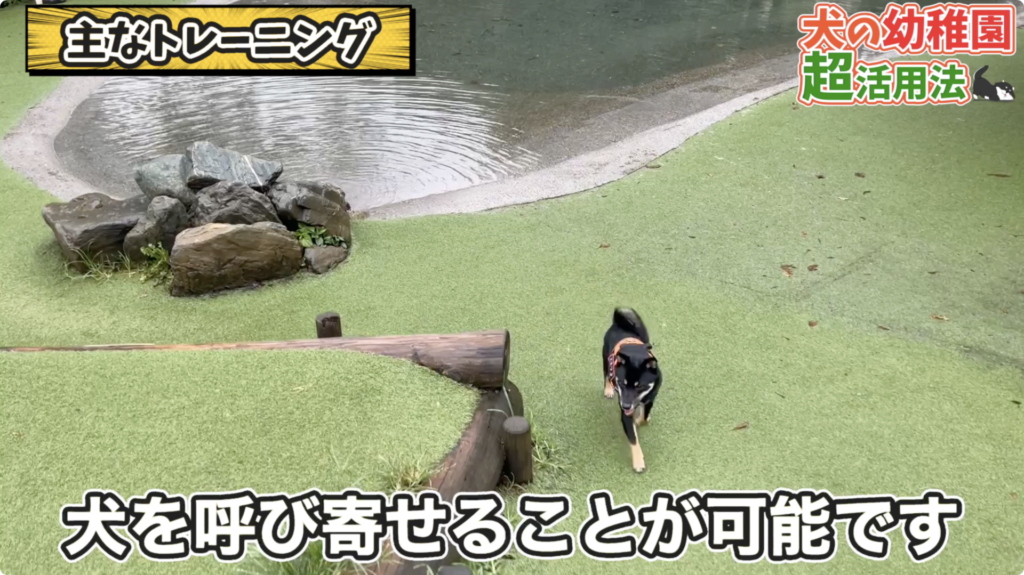
特に、和犬は呼び戻しのしつけが難しいとされており、名前を呼んでも
「来てほしけりゃ、そっちが来い」

と言わんばかりの態度になりがち。
※詳細は「柴犬学 – 柴犬あるある②」をご覧ください。

忙しい日々でも合間を縫って意識的に呼び戻し訓練を行うのが望ましいところですが、幼稚園でトレーニング済みであると飼い主の負担も軽減するので助かっています。

それでもなお、名前を呼んでもやって来ないことがあるのは、柴犬などの犬種特性に依るものかもしれません。

グルーミング

ブラッシングや爪切りなどの基本的なケアを行えるようにするため、グルーミング全般も幼稚園で練習しています。
初めの頃は、ブラシで体を撫でようとするだけで噛もうとしてきました。


今では、ブラシで軽く撫で始めると頭を床に擦り付けて気持ちよさそうにしてくれています。
また、お迎え当初には苦労した爪切りも、回数を重ねるに連れて、(やや嫌がりはするものの)本気噛み等されることなくパチパチと爪を短く、綺麗に整えることが可能になります。


こうした日常的なケアについても、トレーニングの機会が増えることのメリットはあったように思います。
社会化

多くの場合、幼犬期の社会化を目的として犬の幼稚園に通わせているようです。
特に柴犬などの和犬は、社会化期が短いことから、しつけが難しいとされています。


できるだけ早いうちから、他の犬や人とコミュニケーションをとれるようになることを目的に通っています。
柴犬は無駄吠えが少ない犬種のため、吠え癖の矯正などは必要性がありませんでしたが、よく吠える子は社会化を通して吠える対象や吠える機会を逓減させていくことで変化を実感できるかもしれません。

車やバイクなどの生活騒音にも慣れることで、無駄吠えや極端な恐怖心を持つことなく平然と過ごせるようになりました。


家でお留守番しているだけでは学ぶことができないような経験を幼稚園の中で体験することで、お出かけや旅行の際にも落ち着いて過ごせるようになってきた気がします。

犬慣れ・人慣れ

他の犬や他の人と、とにかくたくさん触れ合うことで、犬慣れ・人馴れの効果が期待できます。
まだ好奇心旺盛な幼犬のうちに、多くの犬と出会い、人の優しさに触れることで、恐怖心を抱かないよう環境づくりを意識する必要があります。
実際に、幼稚園に通い始めてから半年が経つ頃には、他の犬や他の人に恐れることもなく、積極的に絡んで遊びあったり、絡んでもらったりしています。
今では、
犬を見ると「お友達?」


人を見ても「お友達?」


となるほど犬も人も大好きな柴犬になりました。

体力発散・ストレス解消

毎日の決まった時間・決まったルートでのお散歩だけでは削りきれない小柄な柴犬の体力を、幼稚園でがっつり削ってもらう目的もあります。

特に、プレイタイムでお友達と賑やかに遊んでもらうことで、社会化だけでなく体力発散とストレス解消を同時に達成してもらい、お家に帰ったらご飯と歯磨き後は爆睡するほど疲れています。

毎日お留守番するだけでは得られない学びを得るだけでなく、有り余る体力を発散するとともにストレスも解消するという目的で通園するという利用方法も一つのアプローチと言えるかもしれません。
飼い主自身が変わる


【変化が無いと感じる理由】
- 自宅で過ごす時間のほうが長いこと
- 学びの定着には頻度と期間を要すること
- 犬は人によって態度を変える傾向があること
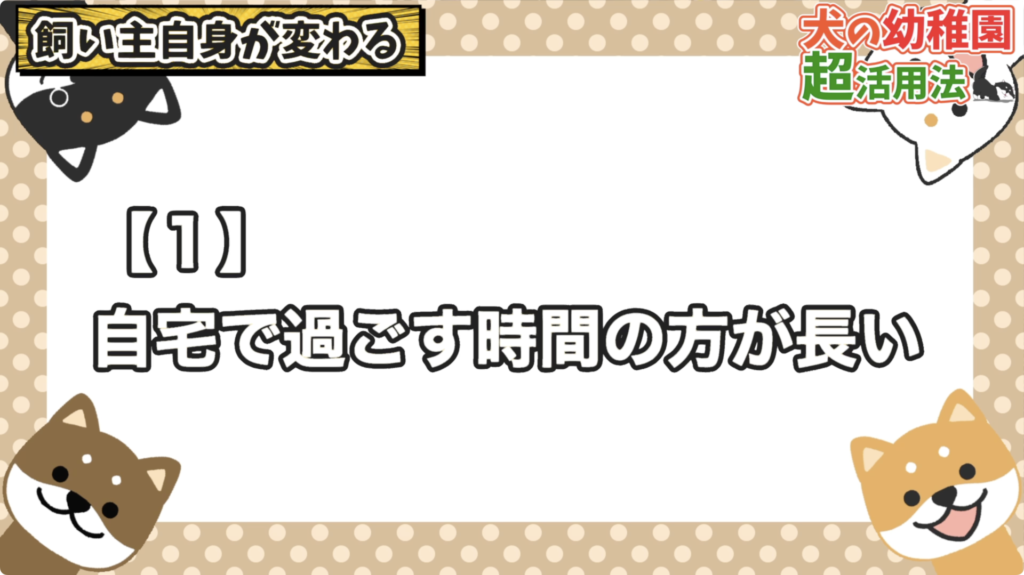
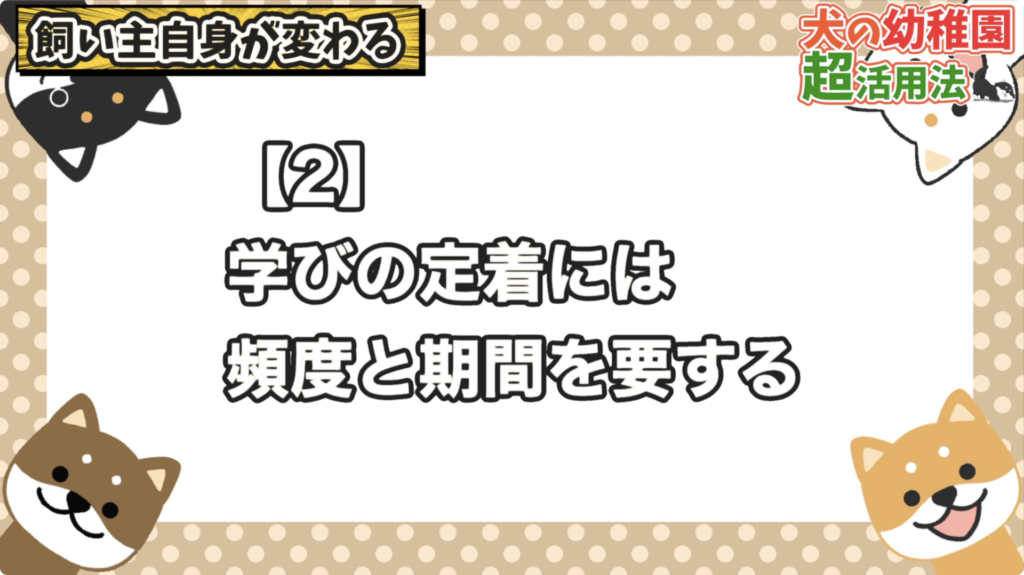
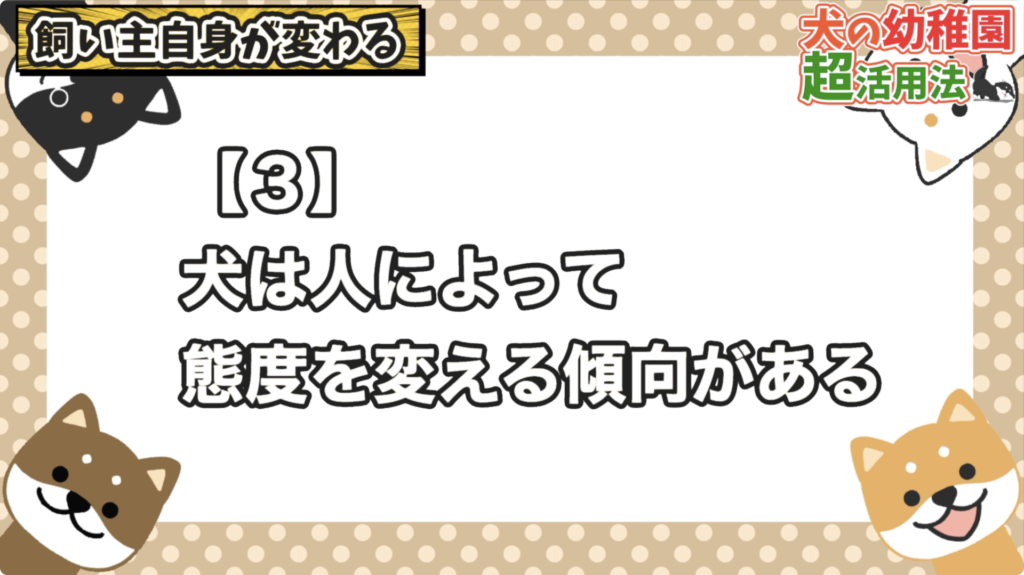
これらの要因から、大局的に見ると、犬の幼稚園に通うだけでは大きな変化を実感しづらいと思う場面もあるかもしれません。


そうして、「犬の幼稚園に通っても意味がない」という意見もまた「正しい」となるのです。
重要なのは、犬の幼稚園に通うことで、「飼い主自身も変化するきっかけ」を得ることです。

自宅に帰ってきたら、トレーナーにその日に行ったトレーニングの内容や様子などを確認し、自宅でも継続して同様のトレーニングを行う必要があります。


そうすることで、犬自身の変化を飼い主が着実に捉えることができるようになります。
また、犬が幼稚園で学んだことを反復することで、再現性の保持にもつながる効果が期待できます。


まとめ

犬の幼稚園に通い始めて、早1年半。


犬の幼稚園に通う中で、多くのことを学び、自然とできるようになっていました。


犬の幼稚園に通う、通わないについては、何を求めるかによって変わってきます。

噛み癖や吠え癖の矯正、社会化、歯磨き、グルーミングなど、意識的にやっておかないと後々困ることが多い一方で、幼犬期はあっという間に過ぎていってしまいます。


犬の幼稚園に通わせるか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

では、また次の動画でお会いしましょう!

じゃあね!











